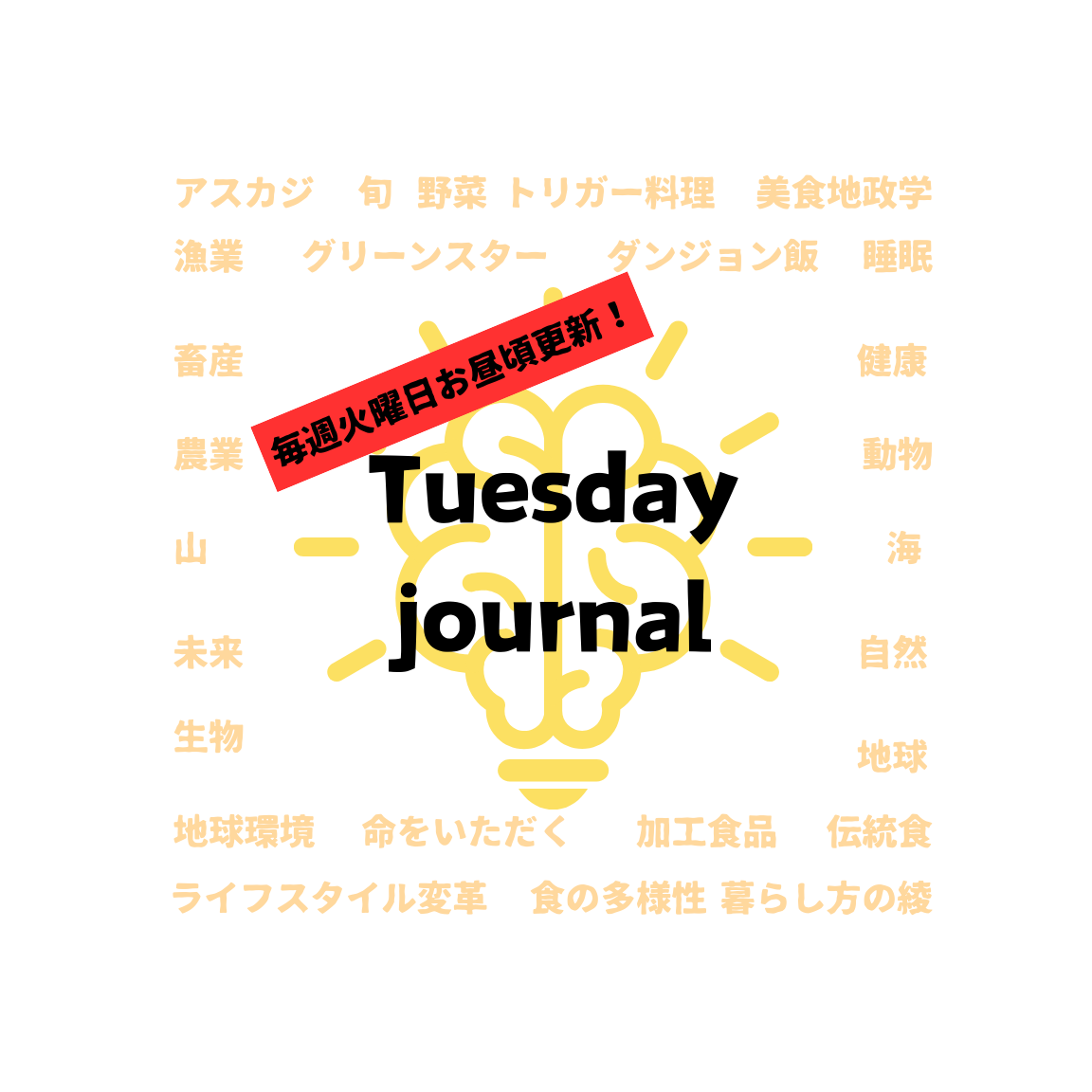Hello!古岩井です。
Tuesday journal vol.3ではVEGAN について書きました。
今回は精進料理をざっくりと書いていきます!
みなさん、「精進料理(しょうじんりょうり)」を食べたことはありますか?
これは仏教の教えに基づいた、お肉や魚を使わない植物性の料理のこと。お寺で食べられる料理として発展してきましたが、健康的な食事としても注目されています。
なぜ健康的な食事と言われるのか。
今回は、精進料理の発祥や歴史、そして現代の精進料理との違いからその辺りを感じ取っていただけると思います。
【目次】
1.精進料理のルーツとは?
2.昔の精進料理と今の精進料理、何が違う?
3.代表的な精進料理
4.五味(ごみ)とは?精進料理の基本となる味のバランス
5.精進料理の基本
6.まとめ
1.精進料理のルーツとは?
精進料理の歴史は、仏教の伝来とともに日本にやってきました。
仏教とともに伝わった食文化
6世紀ごろ、日本に仏教が伝わると「殺生(生き物を殺すこと)」を避ける考えが広まりました。仏教では、動物の命を奪うことは良くないとされるため、お坊さんたちは肉や魚を食べずに、植物性の食材だけを使った料理を作るようになったのです。
- 臭いが強いため気を損ない、修行の妨げになると考えられている
- 刺激が強すぎて心身のバランスが崩れるため
- 欲情や怒りを仰ぐ煩悩への刺激物とされている
- 殺生につながる三厭(さんねん)とされている
鎌倉時代:禅宗の影響で広まる
鎌倉時代になると、精進料理のスタイルも広まりました。禅宗では食事も修行の一環とされ、質素でシンプルな料理が大切にされました。
ミニマリズム※な生活の広まり
この時代に、今でもお寺で受け継がれている「一汁一菜(一汁三菜)」の食事スタイルが生まれました。
※ミニマリズム(minimalism)とは、無駄なものを省き、必要なものや本質的なことにフォーカスする考え方です。
2.昔の精進料理と今の精進料理、何が違う?
精進料理って堅苦しい!
いいえ!
時代とともに、精進料理も少しずつ変化しているので試しやすいものも続々登場しています。
それでは昔と今を比べてみましょう。
昔の精進料理
🔹 より質素でシンプル
→ 基本は「ご飯+汁物+漬物」、副菜は少なめ。
🔹 修行の一環としての食事
→ 「食べること=修行」なので、味付けも薄めで慎ましい食事。
🔹 旬の食材を大切に
→ 冷蔵技術がないため、その季節に採れるものを活かした料理。
現代の精進料理
🔹 種類が豊富になった
→ 天ぷらや豆腐ハンバーグなど、お寺以外でも楽しめるメニューが増加!
🔹 おしゃれで洗練された
→ 最近は「ヴィーガン(完全菜食)」の影響を受けた、カフェ風の精進料理も登場。
🔹 栄養バランスを重視
→ 昔よりも食材の種類が増え、たんぱく質やビタミンを意識した料理が増えている。
3.代表的な精進料理
では、具体的にどんな料理があるのでしょうか?
① 野菜の煮物
旬の野菜を昆布や干し椎茸の「精進出汁(しょうじんだし)」で煮込んだ、優しい味の一品。
② ごま豆腐
すりつぶしたごまを葛粉(くずこ)と混ぜて固めた、もっちり食感の料理。
③ 野菜の天ぷら(精進揚げ)
にんじん、なす、れんこんなどをカラッと揚げた料理。卵を使わずに作るのが特徴です。
④ がんもどき
潰した豆腐に野菜を混ぜて揚げたもの。肉の代用品としても満足感があります。
⑤ けんちん汁
ごぼうや大根、にんじんなどの根菜をたっぷり入れた汁物。精進出汁や味噌で味つけします。
とってもシンプルで、家庭料理に近い料理ですが精進料理には「基本」があります。
では、その基本とは何かを見ていきましょう。